吉本隆明の猫随筆「フランシス子へ」など [本]
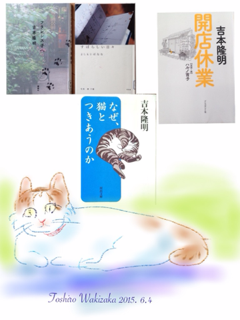
吉本隆明は、1924年東京 月島生まれ 。 88歳 で2012年没 した。東工大卆 の詩人 、文芸批評家 、思想家。「戦後思想界の巨人」、「知の巨人」と評される。漫画家ハルノ宵子は長女、作家よしもとばなな(1964〜)は次女。
肝心の詩や思想にかかる著書は読んだことはないので、それらを語る資格はもとより無い。
随筆「老いの超え方(2006朝日新聞社)」、「よせやぃ(2007ウエイツ)」は読んだ。「老いの超え方」では、「老人というのは、もう人間ではなく超人間と考えるべし」という文章だけをなぜかしら覚えている。あとの一冊は何も記憶がない。
最近、「知の巨人」は無類の猫好きだったと知って、猫随筆を図書館で検索し借りてきて何冊か読んだ。自分も猫と暮らしているので、猫随筆はかなり読む方だが、吉本隆明の猫随筆は少し他と趣が異なる。まず惑溺ぶりがすごい。「猫化」している、とさえ思える。「知の巨人」との落差が大きいので、思わず頤が緩む。
まず「フランシス子へ」(吉本隆明 講談社 2013)。
フランちゃんことフランシス子は、吉本の愛人と言われていた(長女ハルノ宵子)雌の猫である。
その愛猫フランシス子が死んで9ヶ月後、2012年3月吉本が逝く。
この本には、老人の老猫への思いのたけが、めんめんと書かれている。
編集者はこの本を「女こどもの本」と言うが、生と死の狭間にあった吉本・シャーマンの言葉を綴ったもので軽い本ではないと、長女のハルノ宵子はあとがきで書いている。その通りだと思う。
親鸞上人や武田泰淳の話が出てくるからではなく、老人が老猫に話しかける言葉が、ある意味重いのだ。
一つだけ引用すれば十分であろう。
「フランシス子が死んだ。
一匹の猫とひとりの人間が死ぬこと。どうちがうかっていうと、あんまりあんまりちがわねいねえって感じがします。おんなじだなあって。
どっちも愛着した者の生と死ということに帰着してしまう。」
次は「なぜ、猫とつきあうのか」( 吉本隆明 河出書房新社1999)。
こちらは、吉本が比較的元氣な時のもの。猫随筆というより吉本へのインタビュー・猫編である。
「動物性という言い方をすると、人間はやっとこさ動物が持っている本能的習性みたいなものから脱却したばかりで、ー動物性の上に何かを意識的に築いてヒューマニズムみたいなところまで、やっとこさきたということになるんじゃないでしょうか。
動物性がまったくなくなるまで解脱したわけじゃないですから、ふとした瞬間に動物性が強大な現れ方をすればー弱者をますますたたきのめしたくなっちゃったとかーヒューマニズムの名のもとに人間を惨殺したりー今の人間の段階はそんなところだという言い方もできるんじゃないでしょうか。」
次女の作家、よしもと ばなな が「あとがきにかえて」で次のように言う。
「それにしても、この本の、なんとなく盛り上がらないというか、無理がある感じが、なんとも間が抜けていてよく、妙に味が出ていますね。作っている人たち(全員父を含む)の困った気持ちが伝わってくるようだ。
しかし、姉のイラストはさすがにうちの猫たちを的確に描いていて、今はもういない猫の懐かしさに涙が出た。写真よりよほど生々しい。」
確かに吉本が猫博士というくらいの漫画家の猫挿絵は素晴らしい。長女は晩年の思想家の良き世話係でもあった。
ついでに借りて読んだ本。
「開店休業」(吉本隆明 追想・画 ハルノ宵子 プレジデント社 2013)を読めば、それがよく分かる。
この本は、吉本隆明が料理雑誌 dancyu誌 に2007年1月から2011年2 月まで4年間書いた随筆である。本の題名は途中体調を崩して、一時中断したりしたところから付けられた。
吉本の文章に長女のハルノ宵子が追想コメントを付していて、一段と味を濃くし、深めている。
吉本はこの連載を終えて、ほぼ1年後の2012年3月に逝去している。
吉本(家)の食べ物の話ばかりだが、猫の缶詰めの話もある。また、食べ物の話だけでは、たねも尽きたか猫の文章もある。吉本が小さい時から猫と遊んでいた(逢いびきしていた、という)こと、猫族との同族体験を愉しんだことを懐かしみ、老人になってもなお猫と同化(!)して暮らしている様子がうかがえて、楽しい。(猫との日々)
本題の食べ物の話は、同じ老人には頷くところがあって面白いが、知の巨人なるが故か、理解に苦しむ話の展開もあって悩ましい。
「ときに私は、自分が脳で食べ物の味をわかるのではなく、目にする色調と舌触りで感じているいるような気がして、しきりにこだわっている。(野菜の品定め)」
これなら難しくはないが、次の歌の引用になると自分には理解し難い。
「食材の良否の体験は、経済や政治の問題になるが、味覚の問題は文化と文明の民族性、その固有さと普遍性の問題だと言えそうな気がする。
古歌にも「駒とめて 袖うち拂ふ かげもなし 佐野のわたりの雪のゆふぐれ」と、あるではないか。 (甘味の自叙伝)」
「おかしなことをやってばかりで、文句を言われぬよう、太宰治が鬱勃たる雄心の歌と呼んだことのある、吉井勇の歌を添えておく。
紅燈のちまたに往きてかへらざる ひとをまことのわれと思ふや
(老いてますます)」
さて、最後は、よしもと ばなな著「すばらしい日々」( 幻冬社 2013)。
作家が両親を相次いで失くして間もない頃の日常を綴った随筆。吉本隆明は、猫を可愛がるのは遺伝するのだと書いているが、娘一家は犬を飼っている。遺伝子は猫と犬を区別しないのであろう。この本には猫の話は全く出てこない。
父を失った娘の哀切の気持ちがひしひし伝わる。男の子とは随分と違うな、というのが読後感である。
これらの本を読むと吉本家の様子がだいぶ分かる。吉本ファンには興味が尽きないであろう。
しかし、ふと気になったのは余り表に出てこない吉本の妻、二人の姉妹の母の特異なキャラクターである。
食べることが嫌い、そのせいで料理を作ることは嫌いという女性。猫は嫌いではなかったのだろうか。インタビューしてみたい。
吉本は不平も言わず、著作の傍ら手料理で不味い焼きたまごなどを作っていたようだ。二人の姉妹が料理嫌いにならなくて、幸いであったというものだろう。
2015-06-04 09:05
nice!(0)
コメント(0)
トラックバック(0)




コメント 0